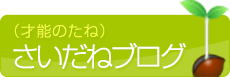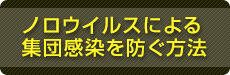2024年
「不機嫌」コミュニケーション
『人間の最大の罪は、不機嫌である』
ドイツの詩人・ゲーテの言葉です。
学生の頃、最初にこの言葉に出会ったときの
ハッとした感覚を今も覚えています。
また、どこで聞いたのか忘れてしまいましたが
このような言葉にもハッとしました。
_____
男性は、思い通りにならないことが原因で
不機嫌になることが多く、それに対して、
女性は、思いが伝わらないことが原因で不機嫌になることが多い。
_____
「不機嫌」の源・理由を提示されると、確かに!と腑に落ちます。
かと言って、男性女性などの性差ではっきり分けられるものでもなく
「傾向」というふうに捉えています。
「思い通りにならない」「思いが伝わらない」
このどちらも原因で、不機嫌になった経験は
誰でもあるのではないでしょうか。
対人関係において、不機嫌をコミュニケーションの手段として
使ってしまうこともあります。
但し、不機嫌というコミュニケーションは、
ポジティブなコミュニケーションよりも圧倒的に伝染力が強いのです。
人から人へ、またその先に人へとどんどん広がっていきます。
この伝染力の強さが、ゲーテの言うところの
不機嫌が「最大の罪」となる所以なのかもしれません。
「思い通りにならない」と「思いが伝わらない」のどちらにも
「思い」が入っています。
と言うことは、「思い」を「言葉にする」ということが大事ではないでしょうか。
思いを不機嫌というノンバーバル(非言語)コミュニケーションではなく
思いをバーバル(言葉による)コミュニケーションに変えていくことが大事です。
まわりに気を遣わせたり、緊張感や不快感を与える
不機嫌コミュニケーションではなく
まわりがリラックスする、尊重しあえる、
笑顔が広がるコミュニケーションを心がけたいですね。
フキハラ(不機嫌ハラスメント)という言葉もなくなるように。
いつまでもどこまでも
新年度がスタートして早1ヶ月です。
環境が変わったり、初めての仕事を経験している方、
他にも様々な変化を経験中の方も多いのではないでしょうか。
「変化」をどのように捉えていますか?
知らなかったことを知ることができる。
出来なかったことが出来るようになる。
知っている、出来ている、という世界から飛び出して
思い込みを外すチャンスです。
いつまでも、どこまでも
知らないことや出来ないことが待っている。
知らないこと、出来ないこと・・・未知の経験の世界が広がっている。
変化は、世界に対する認識を変えてくれます。
認識が変わると、未知のことに好奇心を持てます。
いつまでもどこまでも、好奇心を持って、
いろんな経験をしていきたいですね!
それって、頭の中にしかないよ
書店に入ると「キキ&ララの『幸福論』」という本が目に留まり、
優しい色合いに思わず手に取りました。
どのページにも、キキ&ララのイラストが満載です。
イラストだけでなく、フランスの哲学者アランの『幸福論』が
平易な言葉で書かれている本です。
ぱっと開いたページにはこう書かれていました。
「過去への後悔や、未来への心配。
それって、頭の中にしかないよ」
後悔や心配は、頭の中にしかない。実体がない。
私たちは、どうしてもこの実体のないものを作り出してしまいます。
そして、それをあたかも実体のあるもののように扱ってしまいます。
このアランの言葉を聞いて、確かにそうだと納得しますが、
おそらく今後も、過去への後悔と未来への心配は出てくると思います。
出てきてもOKです。
出てきたときは、
「あっ、これって頭の中にしかないものだ」と気づけるようになればいいのです。
実体のないものを客観視できるようになっていければいいのです。
実体のないものを自分で作り出して、それに振り回されていることに気がつけば、
過去でも未来でもなく、「今」に焦点を当てて、行動を起こす一歩につながります。
未来を考えるときは、未来への心配ではなく、
2月27日の学びコラムに書いた
「未来の笑顔をつくる」を頭の中で考えませんか?
「笑顔=よりよい未来」へ向けて、小さなことから今、行動を起こしませんか?
「過去への後悔や、未来への心配。
それって、頭の中にしかないよ」
キキ&ララが耳元でそっとささやいてくれます。
平安ガールフレンズ
もうすぐ桜が咲き始める頃です。
桜の花を思い浮かべるだけで、心がふんわり軽くなります。
NHK聞き逃し配信で
朗読の世界・酒井順子『平安ガールフレンズ』を聴いています。
平安時代を生きた上流作家・紫式部と清少納言。
このふたりの性格分析の切り口が鮮やかでとても面白いです。
千年前の人物というより、ふたりを身近にいる人のように感じられます。
当たり前と言えば当たり前ですが、
千年前にも人間関係はいろいろあったのだと…
だから親近感をもって共感できるのですね。
平安時代と現在では、物理的な世界は様変わりしてしまっていますが
人と人の関係や人の心は、平安も令和もそれほど変わっていないと感じます。
「源氏物語」や「枕草子」が、千年の時を超えて読み継がれるのは
どうしてなのか理解が深まりました。
平安ガールフレンズは、心を軽やかにしてくれます!
未来の笑顔をつくる
友人のお母さんが急遽入院し退院後に
その友人と会いました。
もう少し遅かったらどうなっていたことかという状態から、
無事に退院することができたと友人は心の底から安心していました。
その姿を見て、私も本当によかったと安堵しました。
そのあと、お互いに笑顔で楽しく話が弾みました。
友人と私のこの楽しい時間をつくってくれたのは、医療従事者の方々です。
退院できていなかったら、会うことはできていなかったと思います。
医療従事者の方々の「仕事」のおかげです。
「仕事とは、誰かの未来の笑顔をつくること」
友人の安心した様子を目の前にして、
友人と会えて楽しく話ができて、あたらめてそう感じました。
医療従事者の皆さんだけでなく、働くすべての人が、
誰かの未来の笑顔をつくっています。
目の前の人(友人のお母さん)だけではなく
友人と家族、そして私…他にも多くの人たちの笑顔につながっています。
目の前の人はもちろん、その先にいる人たちを想像すると
仕事がもっと楽しくなります。
自分のする仕事の先には誰がいるのかを想像すると
目の前のひとつひとつの仕事に取り組む姿勢が変わってきます。
笑顔をひろげていきましょう!
桃の枝
宅配で野菜とお米を届けてもらっています。
毎年ひな祭りの時期に合わせて、
小さな蕾をたくさんつけた桃の枝も一緒に届けてくれます。
この時期恒例の楽しみになっています。
桃の枝にはこのように書き添えられていました。
「桃は原産地の中国では仙果(神仙に力を授ける果実)と呼ばれ、
邪気を祓い、不老長寿を与えるとされていました」
科学が進歩した今に生きる私たちから遠ざかりつつある考え方です。
そこには、先人達の自然物に対する畏敬の念を感じます。
ひな祭りには、邪気を払い女の子の健やかな成長を願って桃を飾る
…人の心を感じます。
もう女の子ではなくなりましたが、
届けてくれた農家さんの気持ちをとても嬉しく思います。
心の声を聴き取る
朝目覚めてから夜眠るまでのあいだ
「人の批判しない」
「文句言わない」
「愚痴を言わない」
ずっと前に、これをやってみたことがあります。
やってみて、面白いことに気づきました。
そのとき、実際に批判や文句、愚痴は、
言葉となって出てくることはありませんでした。
しかし、言葉にしていないだけ、ということに気づきました。
批判していました!
文句を言っていました!
グチってました!
心の中で。
ニュースを見ては
(心の中で)「政治家という人たちは・・・」
電車を降りるとき、靴のかかとを踏まれて
(心の中で)「わっ!靴脱げた!危ないやん!踏んだの誰??」
真っ黒焦げの炭と化した食パンを目の前にして
(心の中で)「トースターやりすぎ~!」(他責もいいところです)
言葉にしていないだけで、
心のなかでは、批判、文句、愚痴をタラタラと言っていました。
それまでは無意識だったので、
このことに気づいたときは自分でもビックリしました。
ただし、ここで、出てきた心の声を批判したり、心の声に文句を言ったりと
自分自身の心の声を批判しないのがミソです。
二重に批判することになりますから。
まずは、自分から出てくる批判の言葉や心の声に気づく。
そこから始めませんか?
気づく・知ることは、言わないことの始まりです。
気づいて知って意識して、言うことが少なくなれば、
気分よくいられる時間が増えるということです。
その時間をどんどん延長していきましょう。
心穏やかに、心元気な1年を!
澄み切った冬の空気を胸いっぱい吸い込むと
冬の早朝、澄み切った空気を胸いっぱい吸い込むと
体の中もスッキリきれいになっていくように感じます。
それだけで、朝から贅沢な気持ちになります。
私たちは、日常の小さな瞬間に、
小さな幸せを見出すことができます。
日常の「当たり前」を大切にしようとする心でいると
どんなときも気分よくいられますね。
自分の身にも、いつ何が起きてもおかしくないからこそ
いつも気分よく、そして平静でありたいと思います。