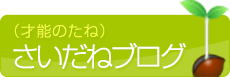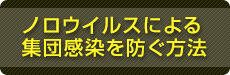2023年
今年の満足
今年はどんな1年でしたか?
不満に思うこともあったかもしれませんが
それ以上に満足もたくさんあったと思います。
今年はこんなことに恵まれたなぁ。
こんな満足感・充足感があったなぁ。
軽く振り返ってみませんか?
大満足はもちろん、小さな満足も探してみてくださいね。
たくさんたくさん出てくると思います。
恵みや満足を振り返ると、感謝の気持ちが自然と湧いてきます。
新しい年をあたたかい気持ちで迎えたいですね!
誰もが長編小説執筆中
「人生」を「長編小説」に見立てると
今日の一日は
1ページ分かもしれないし、
ほんの数行なのかもしれません。
但し、この1ページがなければ、この数行がなければ
私たちそれぞれの人生という長編小説は成り立たないのです。
1ページ、ほんの数行でも、大事な大事な一部分です。
最後に人生を振り返るとき
どの1日も、どの瞬間も、飛ばすことができない、
なかったことにするなんてできない、
と実感するのでしょうか?
物語を閉じるときでないと分からないですね。
さて、今からは白紙の状態です。ストーリーは未知です。
どんな1行1行になるのか、どんな1ページになるのかは決まっていません。
今から、そして新しい年も、この長編小説の続きは日々記されます。
誰もがそれぞれの物語を持っていて
唯一無二のかけがえのない1冊になるのだと思うと
自分に対しても、他者に対しても、敬意を込めた優しい眼差しになります。
そして、他者の1ページに自分が登場することもあるのだと思うと
相手の人生をよりよく彩る一部でありたいという気持ちになります。
そういう気持ちで人を見ると、世界がよりよい方向へむかう
小さな一歩になるのではないだろうかと思っています。
「今」に集中
もう何年も前のことですが、年末の大掃除の頃、
耳に留まったご高齢の女性のつぶやきが今も印象に残っています。
「ここ(カフェ)で、お茶飲んでる時間があるんだったら、
窓ガラスの一枚でも拭けばいいんだけれど・・・」
人は常に「何かをする」ことに追われて
今を十分に楽しめないでいると思った言葉でした。
私たちは楽しいことをしていても、
ついつい気になっていることに意識が向いてしまいます。
「今」に集中できないでいます。
仕事中も、今の仕事をしながら、次はあれをしてこれをして…
と「すること」を考えています。
家でも、食事の支度をして、洗濯して…と次の家事のことを考えます。
良い悪いでなく、私たちの日常生活は「何かをする」を軸にしています。
何かをすることの連続によって生活を進める習慣が身についています。
なので、「今」にいる習慣がなく、「今」にいることに慣れていません。
慣れていないので、せっかくのお茶や友達とのおしゃべりを楽しんでいても
ふと窓ガラスが拭けていないことに意識が向いて
「今」に居心地よくいられなくなります。
今にいることに慣れていないので
今、居心地がよくないことにもなかなか気づけません。
誰もが経験していると思いますが
仕事でも遊びでも、「今」に集中していると充実感があります。
まずは、1日1回意識的に、思いきり今に集中してみませんか?
今に集中して今を楽しんで
今以上に充実した笑顔になってほしいと思っています!
秋空を見上げて
ふかふかの落ち葉を踏む音が耳に心地よい季節になりました。
秋の空はきれいなので、他の季節よりも空を見上げる回数が増えます。
見る回数が増えたことで、空を見ていない時間に思いを巡らせます。
私が空を見ていないときも
空は何もかもを包み込むようにゆったりとそこにある。
こんな想像をすると、空という超特大の優しいマントに包まれているようで
穏やかなゆったりとした気持ちになれます。
遠出しなくても、いつも自然に触れていることを思い出します。
いろんな「○○の秋」がありますが、「想像力の秋」を楽しんでいます 笑
小さい秋、小さな発見
小さい秋、見ぃつけた♪
日常でのちょっとした小さな発見をふたつ。
一つ目は「行動の変化」の小さな発見。
秋の爽やかな空気が気持ちよく、外を歩いているとき、
気づけば、ゆっくりと深く呼吸しています。
猛暑の夏にはまったくしようとも思わなかった行動です。
季節によって、ちょっとした行動も変わるのですね。
二つ目は「心の変化」の小さな発見。
マンションの中庭の植え込みが、砂利敷きの石庭風に変わりました。
元々あった草木花のことを思うと、少し心が痛みます。
しかし最近、砂利のあいだから、いくつものクローバーが顔を出し始めました。
種が飛んで来たのでしょうか? 明るい気持ちで見守っています。
小さな変化の発見は、毎日を豊かに楽しくしてくれます。
“代わり映えのない毎日”というのは存在しないです。
少しスローダウン
家族や大切な人に、何か問題が起きると
気が気ではありません。
家族や大切な人とのあいだでは
自他の境界線がにじみやすいものです。
境界線がにじむがゆえに、問題を解決しなければ、
といつの間にか、自分事として捉えてしまったりします。
そうなると、話がややこしくなります。
何か問題が起きたとき、まずは、ゆっくりと呼吸し息を整えて
こう自分に問いかけましょう。
「この問題は、誰の問題?」
そうすると、問題自体と少し距離が取れます。
俯瞰・客観視すると、状況を適切に捉えて考えることができます。
『私は他人の問題を深く心配したとしても、
それに巻き込まれない』
という捉え方も、距離感や心の余裕をもって
適切に考え判断・行動するのに役立つのではないでしょうか。
少しスローダウン、一呼吸置いて
「この問題は、誰の問題?」から始めませんか?
慌てなくて大丈夫です。
中秋の名月
昨晩は中秋の名月。
美しい満月を眺めることができました。
しばらく月を見ていると、不思議な感覚になります。
月と自分が同じように存在していることに不思議さを感じます。
夜だけではなく、今この瞬間も同じよう存在しています。
目に見えないから、「無い」のではない。
無いものにしてしまっていることが、たくさんありそうです。
そこに、大切な何かが「在る」かもしれませんね。
前を向いて!
ラグビーワールドカップ、イングランド戦で
日本は敗れましたが、試合終了直後の選手たちの
コメントが印象的でした。
キャプテンの姫野選手
「大事なのは、下を向く時間はない」
松田選手
「負けを活かして」
リーチ マイケル選手
「悔しいけれど、落ち込む必要はない。
ポジティブに切り替えていく」
どの選手もメンタルの強さを感じる言葉です。
そして、未来(次のサモア戦)を見ている言葉です。
失敗したとき、辛いことがあったとき、しんどいとき、
下を向くというのは、そのことに留まってしまうということです。
「下を向いてるな」と気づいたら
前を向いて、それでも頭が下を向いてしまうなら
思いきり、上(空でもいいですね)を見上げて
失敗を活かそうとポジティブに切り替えていきたいものです。
ポジティブに切り替えるには、「前を向く」=「未来を見る」。
ここがポイントです!
前を向く(未来を見る)と、ブレにくくなります。
ブレにくいということは、メンタルが安定するということです。
10月開催セミナー【伸びる人が育つコミュニケーション】
10月28日(土)14:00~、セミナーを開催します。
今回のテーマは『伸びる人が育つコミュニケーション』です。
++++++++++++++++
日々“人の成長”を支援するなかで
『伸びる人は、自分で考えて行動する人』だと実感しています。
また、誰もが「よりよく変わりたい」と無意識では思っています。
成長を望んでいます。
けれど、一人では限界があり、成長したくても、変わる“きっかけ”は
自分ではつくりにくいものです。
きっかけさえあれば、人は変わることができます。
自分で考えて行動し伸びる人になっていくためのきっかけを
あなたがつくってあげませんか?
初対面でも話しやすい安心感のある場で、和やかに対話・交流しながら進めますので
お気楽にご参加ください。思いきってのご参加も大歓迎です!
〘こんな方におすすめです〙
● 成長支援のためのかかわりを見直したい
● 教育・指導に活かしたい
● 職場の伸び悩んでいる人をサポートしたい
● 対人支援力を高めるきっかけがほしい
● 互いに成長しあえる関係性やチームをつくりたい
<セミナー内容>
◆ 伸びていく人」「伸びにくい人」とは
◆ 人が伸びるとき
◆ 伸びる人が育つコミュニケーション環境
◆ 成長支援のためのかかわり<日 時>
2023年10月28日(土)14:00~16:00
<会 場> オンライン開催(Zoom使用)
※カメラとマイクをオンにしてご参加ください
※つながるかどうかや操作がご不安な方は、当日または数日前に試行もできます。
試行のご希望日時もお気軽にお申し付けください。<定員> 15名様
<参加費> 3,500円(税込)
<お申込み> ※受付終了しました
☆セミナーのチラシPDFはコチラをご覧ください
メンタルと人間関係
メンタルがどんな状態なのかが、人間関係に影響します。
ただ単に「メンタルのよい状態を保とう」からスタートするより、
メンタルの安定・不安定が人間関係にどう影響するのかを理解してから、
メンタルを安定した状態にしていくほうが効果的です。
どのように影響するのか想像して、行きたい先がはっきりしていると
進みやすくなります!